「そんなにきれいだったんなら、なんで僕も起こしてくれなかったんだよ」
「あんまりよく眠ってるから、そっと出てってやったんだろーが。俺は俺なりに気ぃつかってんだぜ」
「気をつかうっていうんなら、そんなに得意げに言わなくたっていいじゃないか」
早起きした塚田とじいちゃんの二人は、僕を置いて朝日を見に行ったらしい。戻ってからきれいだったきれいだったとあんまり繰り返すものだから、ただ一人それを見逃した僕は、さっきからむくれているんだ。
「写真も撮ったから、出来上がったら見せてやるよ」
「いらないよそんなの。その瞬間っていうのは、直接じゃないと分かんないもんだろ」
じいちゃんは黙ったまま、僕と塚田が言い争う様子をただ好もしそうに眺めている。
その時、このツーリストキャンプの係の女性が、薪を抱えてゲルに入って来た。昨夜のように、今朝もストーブに火を入れてくれるんだろう。
係の女性はストーブのフタを開いた途端、けげんな表情で正面にいたじいちゃんの顔を見上げた。ああ、昨夜の馬糞を見付けたな。僕は今まで言い争っていた事も忘れて、塚田と顔を見合わせ笑った。
今朝の朝食にはミルクが付いた。さっそく飲んでみたけど、うー、これはちょっと……。強いにおいが鼻につき、独特の後味がいつまでも残る。
塚田も顔をしかめている。
「これが牛乳? うそだろ? こんなの、どこの馬の乳とも分からねえぞ」
昨日二人で馬乳酒を飲み干したのを思い出し、またも僕らは笑った。僕はもう、塚田に腹を立ててはいない。しょせん悪いのは僕の朝寝坊、すべては低血圧のせいさ。
歯磨きをすませても、牛乳のにおいはまだ口に残る。でもそのにおいはなぜか、さっきほどに嫌なものではなくなっていた。
このにおいの原因は、たぶんウシの食べる草だろう。ハーブのように香りの強いモンゴルの草が、こんなふうに牛乳をにおわせ、そして乳製品を味付ける。この草原をみなもととして、最後には人間までもが、草の香りに染まるんだろうか。
ああ、モンゴルにいるんだなあ。僕は今になってあらためて、モンゴルにいる事を本心から実感した。モンゴルをみなもととしたものが、今自分の体内に流れている。
またそれと同時に、僕をみなもととして、この地に広がってゆくものだってあるはずだ。ここへ来てずいぶん虫に刺されたけど、その血からやがて、新たな命が生まれくる。僕の一滴を受け継ぐその命は、モンゴルの草原を舞台として、これからどのように巡り流れていくんだろう。
……ちょっと空想が壮大になりすぎたな。これも旅の終わりを前にした感傷のせいだ。
これから僕達は、チャーター機に乗り込みウランバートルへ飛ぶ。まだ市内観光が残っているものの、草原を後にするとなると、もう旅も終わりという気分だ。

一時間後、僕らはとぼとぼとタラップを降りていた。早くもウランバートルに着いたってわけじゃない。もう恒例となったトラブルのせいだ。雨上がりの滑走路に、タイヤが埋まってしまったんだとさ。乗務員の一人が、端正な制服姿のままスコップをふるっている。旅の終わりの感傷なんて、見事にぶち壊されてしまったよ。
飛行機が脱出を試みる間、僕ら乗客は少し離れた所で待機する事になった。
「よし、後ろから押してやる」
また妙にはりきっている塚田の提案は、危ないからと却下された。あたりまえだろ、バスとは違うんだから。いったい何をそんなにうかれてるんだよ。
逆に気分のさめている僕は、興奮して脱出劇に見入る人達の中に、いつもの事ながら入って行く事が出来なかった。塚田までが一緒になって健人やムンフツツクと騒ぎ回る光景も、僕は遠くから冷静に眺めていた。
タイヤの掘り出し作業は終わったらしい。エンジンの始動音に振り向くと、飛行機のプロペラが回転を始めていた。
 後方の草がなびき、うねり、そしてなぎ倒される。エンジン音がフルスロットルにまで高まる。機体後部と両翼端が上下に揺れる。とてつもない爆音を聞きながらも、まるで無音の中にあるような緊張感に、僕はじっと固まっていた。
後方の草がなびき、うねり、そしてなぎ倒される。エンジン音がフルスロットルにまで高まる。機体後部と両翼端が上下に揺れる。とてつもない爆音を聞きながらも、まるで無音の中にあるような緊張感に、僕はじっと固まっていた。やがてゆっくり機体は進み始めた。周囲の人達から、エンジン音をもしのぐ歓声がわき起こる。僕も思わず一緒になって手を振り上げかけ、けれど風から顔をかばうようにしてそれをごまかし、きまり悪さを取りつくろった。
顔をそむけた僕の目の前を、見憶えのある青い物が転がって行く。
「おおい白井くん、その帽子拾ってくれえ」
塚田が笑い声でさけんでいる。知らず知らずに僕もまた、笑いながら帽子を追って駆け出していた。そうさ、じつを言えば僕だって、ほんとはみんなと同じでエキサイトしていたんだ。
塚田に帽子を手渡して振り返ると、飛行機は遥か遠く、一キロほども向こうに移動してしまっている。バスはもう帰ってしまったし、あそこまで歩いて行くしかないのかな。
「まあそれもいいだろ。草原の歩きおさめと思えばな」
塚田がなだめるように言った。まるで僕の心を見透かすように。それでも意外と不愉快さはなく、僕はそのまま塚田と並んで歩いた。
すぐ横をすり抜けるように駆けて行くのは、健人とムンフツツクの二人。
「あいつら、もうすっかりなかよしだな」
「ほんといいよな子どもは」
「フッ、そういう白井だって、まだ子どもじゃねえかよ」
「でも、あんなマネが出来るほど子どもじゃない」
「あの無邪気さがうらやましいか」
「まあ、健人の無邪気さが本物かどうかはわからないけど」
「あれが装った無邪気さとなると、うらやましいよりはくやしいよな」
「…………」
塚田はなぜ、こうも僕の心を見透かしてしまうんだろう。
「あの子、ムンフツツクというんだってな」
「ん、……うん。でも健人のやつ、意外と名前も知らずにいるんじゃない?」
「それもまたくやしいか」
「べつに、そんな事……」
はぐらかそうとして、なのに僕はかえってこんな事を口にしてしまった。
「なあ塚田さん、小さい頃からの気持ちは変わらなくても、どうして体ばっかり勝手に成長してしまうんだろう」
ゆうべじいちゃんのつぶやいた言葉が、そのまま僕の言葉になっていた。
けれどそんな思いは、いつまでも自分のありのままでいたいというそんな望みは、僕やじいちゃんに限った事じゃないだろう。たとえば塚田だってきっと……。だからこそ、僕の内心をあんなにも……。
再び飛行機に乗り込んで、僕はじいちゃんとではなく、塚田と並んで座った。
塚田の横顔越し、窓の外には翼が伸びている。旋回する翼の先を、地面が流れて行く。そこに一瞬、白い正方形が流れ過ぎるのが見えた。
「あ、今の、昨日の寺院の白壁だ」
「窓側座るか?」
「いいよ、べつに」
「えんりょすんなよ。どうせ俺すぐ寝ちまうし」
僕と塚田はモゾモゾと座席を交替した。
「塚田さん、朝はごめん」
「何が?」
「起こしてくれなかった、なんて怒ったりして。自分で起きないこっちが悪いのに」
「気にすんな」
「でもさ……」
「俺、けっこう面白がってんだぜ」
「え?」
「白井って、どっか俺に似てる面もある気がしてよ」
「…………」
「気にすんな」
それっきり、塚田は静かになった。そして僕もまた、いつしか眠ってしまっていた。
ウランバートルの空港に降り立つなり、チャーター機の前に勢ぞろいして、記念写真を撮る事になった。
団体旅行の中でも、一番バカらしいのがこれなんだよ。思い出として整えるために仲間を演じるなんて、まったくくだらない。寝起きの機嫌悪さも手伝って、僕は最後尾のはしっこで機体に寄りかかりながら、すっかりシラけきっていた。
ほかの連中はといえば、もうお別れだからという事で、ムンフツツクを囲んで騒いでいる。そんな連中に割り込むようにして、健人があの子のとなりに並ぶのが見えた。そむけた顔の目のすみで、カメラのフラッシュがいきなり光った。
続いてもう一枚、と添乗員の言う声に、みんなはあらためて正面向いてかしこまる。するとそのすきをつくように、健人が素早くムンフツツクのほほに顔を寄せた。あいつ、なんて事……。もう一度光ったフラッシュが、見開いた僕の目を真正面から射抜いた。
階段の途中で僕は、健人を列から引っ張り出した。
「なあおい健人くん。きみ、よくあんな事が出来るなあ」
「なに?」
「ほらさっき写真の時に」
「ああ、キスの事」
「……おまえ、なんでそんな平然としてられるんだよ」
「そりゃ、無邪気だからだろ。白井にゃとてもマネ出来ねえよな」
また塚田がずけずけ割り込んできた。僕は負けずに大声でさえぎった。
「分かってるよ、そんなの。でも健人にだって、どっか調子よく演じてる部分もあるんじゃないのかね」
「まさか、こいつはとことん無邪気だぜ」
「さあどうだか」
僕らが目を向けると、健人は首をかしげて笑いながら答えた。
「そんなふうに見えるかもしれないけど、ぼくはただね、その時にしたいと思う事を、そのまましているだけなんだ。あとでしまったなって思わないように」
「けど、その場で好き勝手にやってたとしたら、かえって後悔する事になるんじゃないか?」
「うーん、そうかもしれないけど、でもきっとぼく、おとなになるまで生きていないと思うから」
「…………」
僕と塚田は顔を見合わせた。だから今だけでも思いきり生きようと……。
「この話、お父さんとかおとなの人にはナイショだからね」
そう言って健人は、また無邪気な顔で笑った。作り笑いを返した僕は、ムンフツツクにお別れを言えなかった事を今になって後悔した。
雨粒が、ほこりまみれの窓ガラスにいくつもしがみつく。時おりそれを振り払うように、バスはガクンと車体を揺らす。
とうとう雨になってしまったよ。午後の予定の買い物で、いよいよ街へ出られるというこの時に。外の景色は雨色に沈み、さらに窓の水滴越しにかすんで見える。
またバスがつまずくように揺れた。
「ああ、これこそがバス本来の揺れだなあ」
じいちゃんが低くつぶやく。まあ確かに昨日までのオフロードよりはずっとマシで、こうして景色を眺める余裕だってあるわけだけど。
「でも舗装された道路にしちゃ、ちょっとひどすぎると思わない?」
「優にとってはそうだろう。だがな、日本だってわずか四十年五十年前までは、道路もバスもこんな調子だったものだ」
「わずか五十年ねえ」
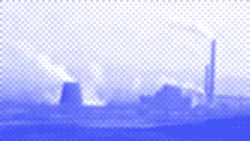 「ああ、どことなく懐かしい情景だな。ほら見てみろ優、あの工場を。煙突からもくもく煙を吹き上げて。昭和の昔、まだ日本が元気だった頃のようじゃないか」
「ああ、どことなく懐かしい情景だな。ほら見てみろ優、あの工場を。煙突からもくもく煙を吹き上げて。昭和の昔、まだ日本が元気だった頃のようじゃないか」「なあじいちゃん、工場の煙なんかを喜ぶなよ。今は環境重視の時代なんだから」
そこへ添乗員が説明を加えた。あれは工場ではなくて火力発電所だと。僕はカン違いのせいでなくじいちゃんとの会話を他人に聞かれた事で、きまりの悪い思いにかられた。
バスは橋を渡り、いよいよ市街地にさしかかった。
黄色っぽい建物が並んでいる。会社か工場のようだ。屋根にはアルファベットとは違う文字の、読めない看板。空き地にはガレキが散らばっている。ゆっくりと点滅する信号機の黄色。街路樹がよく茂っている。雨に濡れた深緑色。その向こうにアパート群が見え隠れする。たいてい三階か四階建てで、窓が小さい。赤いトロリーバスと続けてすれ違う。カサをささないままバス停にたたずむ、大勢の人達。
いつもは際限なくしゃべりまくるじいちゃんが、珍しく黙りこくって外を見ている。きっとこの見知らぬ風変わりな街に、見とれているんだろう。いや、それともひょっとしたら、よく似た雰囲気の昔なじみの街を思い出しているんだろうか。
 道の真ん中に、威圧的な戦車のモニュメントが建っている。それをグルリと回った時、じいちゃんはビクリと身を引いて顔をそむけた。
道の真ん中に、威圧的な戦車のモニュメントが建っている。それをグルリと回った時、じいちゃんはビクリと身を引いて顔をそむけた。「なんだよじいちゃん」
「優、なあ優、……いや、今はよそう」
じいちゃんはまた窓の外に向き直った。バスはもう一度、大きな橋を渡りにかかった。
やがて着いたみやげ物店は、大通りに面しているものの、入り口はただの小さな木のドアだ。バスは壁にこするようにして店の前に停車した。
前のバスからナツオが降りて行く。店のドアを引いてみて、けれどカギでも掛かっていたのか、豪快にノックを始めた。
ドアが細めに開いた。そのすき間に向かって何か話した後、ナツオは振り向いて片手を挙げた。え、ほんとに営業中? だったら入り口に「OPEN」の札でも掛けときゃいいのに。
添乗員は案内するというよりせかすようにして、僕らを一列に並べるとバスから店へと追い込んだ。
「ああ、雨に濡れないようにしないとな」
こんな時でもじいちゃんはあい変わらずのお人よしだ。それこそ首に「お人よし」と書いた札を提げてやりたいくらいだよ。
「親切に、バスをこんなに寄せて停めてくれて。おかげで助かった」
「雨なんて関係ない。どうせ防犯のためだろ」
僕はぶっきらぼうに言った。
「とにかく日本人の団体っていうのは危なっかしいからな」
店に入って振り返ると、店員がまたドアにカギを掛けていた。
店内をひと通り見たけど、たいして気を引かれる物もなくて、僕もじいちゃんも絵ハガキを買っただけで買い物を終えた。それでも全員が買い物をすませるまでは店に閉じ込められ、時間を持てあました。
夕食の後、僕は絵ハガキに向かいペンを握りながら、でもなんとなく気がのらなくてほおづえをついていた。
 じいちゃんはといえばベッドの上にあぐらをかいて、やっぱり絵ハガキをためつすがめつ眺めている。
じいちゃんはといえばベッドの上にあぐらをかいて、やっぱり絵ハガキをためつすがめつ眺めている。「どんな絵ハガキ買ったの? じいちゃんは」
「ラマ教寺院の仏塔に、蒙古相撲の力士に、そして……」
「まったく、じいちゃんらしいチョイスだよ」
「街の風景でもあれば、一枚欲しかったんだがな」
「モンゴルの街なんて今日ひと通り見たけど、ちっとも絵になってないじゃないか。どれもロシア風の建物のモノマネでさ、それでも石造りならまだサマになるけど、ただモルタル塗りたくってごまかして」
「なあ、優は知っているな。あの建物はみな、かつて日本人が建てたのだという事を」
「ん、前に聞いた」
僕はぶっきらぼうにうなずいた。
「シベリア抑留はよく知られているが、蒙古抑留もまた、悲惨なものだったそうだ。零下数十度にも及ぶ寒気の中で都市建設に駆り出され、何千人という抑留者が……」
「前に聞いたったら」
「戦中戦後の蒙古については今もあまり語られないがな、ノモンハン事変も含め、悲劇も多い事を知っておいてくれや、優」
「でもなじいちゃん、だから日本が被害者だなんて事は言えないんだからな」
「ああ、分かっとる、分かっとるとも。双方どちらの国にとっても、言いようのない悲劇だったという事だ」
「悲劇悲劇って気取りすぎだよ。戦争だから兵隊が死んだ、ただそれだけの話じゃないかよ」
僕は冷たく言い放ち、それきりじいちゃんは口をつぐんだ。
ここまで言うつもりはないのに、なぜかいつでもこうなってしまう。感きわまってくるじいちゃんにどう対処すればいいのか分からなくて、僕はつい冷淡に突き放してしまうんだ。
沈黙がさすがに気詰まりになって、僕は少しおだやかな口調で言いそえた。
 「そりゃ、死んだ人が気の毒だとは、僕だって思うけど。で、明日だったっけ? お墓参りは」
「そりゃ、死んだ人が気の毒だとは、僕だって思うけど。で、明日だったっけ? お墓参りは」「ああ、ちょっと行ってくるよ」
「明日も雨になるらしいけど、それでも行く気?」
「もちろんだとも。そのためにはるばる蒙古までやって来たんじゃないか。古くからの約束でもある事だしな」
「そう。……いいね、じいちゃんは。そんなにしっかりした目的があって」
僕は不思議と素直な気持ちになって、本心からそう言えた。じいちゃんもまた、しみじみと嬉しそうな顔をした。
「優にそんなふうに言ってもらえるのが、何よりも嬉しいよ」
「そう?」
「ああ、おまえはほめるにしてもけなすにしても、本気で他人を評するからな」
「そうなのかな」
「そうだとも。その真っすぐすぎる面から敬遠される事もあるだろうが、じいちゃんは立派だと思うぞ。いつでも本気でいる優は」
「そんな……」
そんな事ない。僕は健人ほどにも本気で生きちゃいない。
僕は机の絵ハガキに向き直って、けれどもまたほおづえをついた。
今になって初めて気付いたよ。旅先から手紙を書き送るような友達が、僕にはただの一人もいなかったんだ。もし本当に、僕が本気で真っすぐ生きているなら……。
次の章へ