星の弦 − はちみつ色の世代 1 −
中央広場 >
書斎パビリオン入り口 >>
星の弦3ページ >>
10月21日 金曜日
日曜日が過ぎて、新しい一週間が始まった。
新しい、そんな言葉は今のぼくにはぴったりだ。一つの秘密を共有する仲間ができて、ぼくの毎日は今までとはまったくちがうものになったのだから。
話し合う事があってもなくても、放課後になるとぼくたち五人は集まった。
集まる場所はいろいろだ。理科室、図工室、それから図書室。教室にはたいていほかのクラスメイトも残っているし、一度帰ってからだれかの家に集まるのは時間がもったいない。
そういうわけで、塾のない日の放課後はいつも、ぼくはどこかの特別教室で仲間と顔を寄せ合っていた。
職員室から出て来るなり、工藤は得意げな表情を顔いっぱいにうかべた。後ろにかくしていた手を勢いよく前へつき出すと、指先で銀色のカギがチャリリンとゆれた。
「ラッキー! 借りれたんか」
ミリが手を打ってとびはねた。そうおおげさによろこぶほどの事かなあ。工藤が図書委員だから、図書室のカギくらい先生はすぐ貸してくれるだろうってぼくは思っていた。
「なっ、ユッコたちも仲間に入れてよかったやろ?」
ミリが横から、ぼくの顔をのぞきこむようにして小声で言った。いつかもそんな事聞かれたなと思いながら、ぼくはだまってうなずいた。
星の本をいくつか広げて、みんなはそれを取り囲む。でもそれは、ただのポーズみたいなものだ。図書室の本なんてどれも子ども向けでたいした事は書かれてないし、土曜の夜の観測会が決まってからはそうだんする事もない。けっきょくおしゃべりだけで時間は過ぎてしまう。
でもだからといって、それが不満かっていうとそうでもないから不思議だ。みんなが熱心なのに変わりはないからだろうか。今はみんなといっしょに熱中できるだけで、なんだかうれしい気がする。
「あしたの十五夜、だいじょうぶと思う?」
工藤が言った。彼女はあの流星を十五とよんでいる。ぼくがあれを見たのが十月五日だったから、それにちなんでつけた暗号名なんだそうだ。だから土曜の星の観測会は、十五夜というわけだ。
「だいじょうぶとちゃうか。もう雨も上がりかけとうし、あしたはいい天気になるらしいで」
「それに上野計画も実行しとうしな。な、上野」
「うそ、ほんまにてるてるぼうずなんかつるしたん? あたしじょうだんで言ったんやと思ってた」
有吉がそう言って、工藤と二人で意外そうな目でぼくを見た。ぼくは首をふりかけたけれど、ふとこの二人の目をもっと見開かせてやりたくなって、こう答えた。
「ううん、つるしてはいないんだ。ほんとはそうしたいんだけど、なにしろこーんなに大きいもんだから……」
横でミリとダクテンがニヤニヤするから、ホラだとすぐにばれてしまった。
「それよりさあ、メンバーの証明はできたん?」
工藤がミリにたずねた。メンバーの証明っていうのは、こないだミリが作っていた星の形のプラスチックの事だろう。
メンバーの証明だとか、仲間だけにわかる計画の暗号名だとか、工藤の考える事ってなんだか、低学年の下級生みたいだ。それとも、女の子ってこういうもんなんだろうか。謎とか秘密とかが大好きで、それを仲間どうしで分かち合うっていうのが。
「そんなにすぐにできやしないよ。ふくざつな形で、けっこうむずかしいんやぞ」
「じゃあまだ色もぬってないん?」
話に夢中になっている工藤の横顔を、ぼくは横目でぬすみ見た。
こうして身近に女の子がいるっていうのが、いまだにどこか不自然な感じがする。それはたぶん、前の学校での事が原因だろう。
前の学校のぼくのクラスでは、男子と女子とがすごく仲が悪かった。といっても、ケンカばかりしていたというわけじゃなく、むしろその反対で教室はいつも静かだった。男子と女子とが、ぜんぜん口をきかなかったのだから。
いつからそうなったかはよくおぼえてないけど、たしか四年生の、夏休みの明けたころからだったと思う。それからずっと、三学期が終わるまでそんな状態が続いた。五年になってクラス替えがあって、みんなが新しいクラスになじむまでのあいだは、この分裂もちょっとはっきりしなくなった。けれど夏休みが明けて今ごろは、またもとにもどっているかもしれない。
ぼくはべつに、女子とおしゃべりできなくたってなんとも思わなかった。それでもいつも気をつかって注意してなきゃならないのは、やっぱりちょっときつかった。うっかりミスをすると、ミスというのは女子相手に口をきいてしまう事なんだけど、そうすると、とたんにまわりのみんなからひやかされるのだから。
クラスメイトのひやかし。そんなのなんでもないような事だけど、なぜだかけっこうこたえた。そのうえ、それはどんなささいな事でも見のがされなかった。たとえば、つくえの角に引っかかって牛乳をたおしかけた時にとっさにあやまったり、同じ班の子にそうじの分担をたずねたりするだけでも、思わず顔が熱くなるようなひやかしの言葉がまわりからかぶさってきた。
そしてそんな時でさえ、男子をひやかすのは男子たち、女子をひやかすのは女子たちと分かれているんだから、分裂はまったく徹底していた。
そういうわけで、クラスで男子と女子のあいだで交わされる言葉といったら、学級会の話し合いの時のみょうにていねいな、おしばいのセリフめいた言葉だけだった。とにかく女子相手には、悪口だって言えなかったんだから。いつかある子と口ゲンカになったら、夫婦ゲンカだとか、ケンカするほど仲がいいとか言ってひやかされたっけ。
そんなふうに、男子と女子とがケンカもできなくなるほど仲が悪くなったのは、いったいどうしてだったんだろう。
「……じゃあヨッシーはあまった桃色でもいい?」
「べつにあたしは何色でもええよ」
「じゃあ決まり。ユッコが赤で、ヨッシーが桃色な。それから、それにみんなのイニシャルも入れる事にしたから」
「イニシャル? ええねえ」
「ええやろう。なあんて、ほんとは上野のアイデアなんや」
「えっ、ほんま?」
工藤がこっちを見た。ぼくはあわてて目をそらした。
「へえ、意外」
ぼくはつくえに視線を落としたまま、まだ考え事にふけっていた。
この四人は去年はどんなだったんだろう。この学校ではあんな事はなかったのかな。そんな時、ミリだったらどうしただろう。
そこまで考えて、ぼくはふっとおかしくなった。ミリならまわりがどんなだろうと、ユッコ、ヨッシー、なんて今みたいな調子でいるような気がしたから。きっとまわりのほうがあきらめて、そのうちなんにも言わなくなるよな。
帰りぎわ、ぼくはミリにそんな事をたずねてみようと思った。
「なあミリ、あのさあ……」
「なに? ……なんや?」
ところがどうもうまく言葉が出てこなくて、質問はぜんぜんちがうものになってしまった。
「この前ミリがさあ、謎が深まるって言ったらあの二人が笑ったけど、なんで?」
「え?」
「ほら、ミリの家に集まった時にミリが言っただろ、謎がますます深まるなとか。そしたら工藤と有吉が……」
「あーあー、あれか。あの時な、上野が来る前にもおんなじような事言ってたんやけど、その時ふくらむと深まるがごっちゃになってな、謎がふくまるとか言ってもうたんや。きっとそれを思い出して笑ったんやろ」
「なんだ、ただそれだけ?」
「うん。なんだと思った?」
「ううん、べつに」
たったそれだけの事か。そんなささいな事であんなふうにくったくなく笑い合えるなんて、まったくこの連中は……。
10月22日 土曜日
今日はぼくたちが期待していた通りの天気になった。
空には雲のひとかけらも見当たらず、みつめているとまばたきをわすれてしまうくらい、深い青で広がっている。日の光はまるでやわらかくおし当てられるようにあたたかく、吹く風は心地よくかわいて洗いたての肌ざわりがする。モザイク模様に色付いたサクラの葉が風にふるえるのを見るたびに、ぼくの心のどこかにもさざ波が走った。
雨上がりのこんなにすてきな秋晴れと、今夜の観測への期待とで、表情は思わずゆるんでくるし、視線も知らずに上へ向く。夕方には長大な流星を思わせる飛行機雲を目にして、今までにないくらい大きく胸が高鳴った。もう息も詰まるくらいに。
……でも、それは期待のしすぎだった。
「おいミリ、満月やったらそうと始めから言っといてくれや。こんなんじゃ一等星も見えへんやんか」
ダクテンが手をかざして月の光をさけながら、不満をミリにぶつけた。
「知らんよ、これはユッコのせいだよ。ユッコが十五夜十五夜なんて言うから」
「あー、そういう事言うん? ひっどーい」
「あっゴメン。そうだよな、満月はおおげさやな。ほらはしがちょっと欠けてる」
「なに冷静に解説してんの」
まさか本気じゃないだろうけど、みんなが言い合いをするのは見ていられない。けれどもぼくがあいだに入ってなだめるまでもなく、みんなはもう笑い合っていた。
「ひと月おくれのお月見やな」
「一句よんでみて」
「それよりあたしはおだんごがほしいな」
「あああかん。おれだんごがこわいんや」
「まだそんな事言う。ほら、上野がおこっとうよ」
「べつにおこってやしないよ」
ただあっけにとられてるだけだ。
それにしても、月の光がこんなに明るいなんて知らなかった。どうして今まで気付かなかったんだろう。なんだか生まれて初めて月をあおいだような気持ちになった。辺りはしもにおおわれたように白い光に照らされて、足もとにはくっきり影が落ちている。そして空は全体にぼんやりとした光がこもり、星はほとんどかき消えている。
「こらまったくあかんなあ。カシオペア座はどこや?」
「ほらあそこ」
 「あああれか。じゃあ、えーと、あれが北極星やな。ちょっと星座盤貸りるで」
「あああれか。じゃあ、えーと、あれが北極星やな。ちょっと星座盤貸りるで」
ダクテンはミリから星座早見盤を受け取ると、空と見くらべながらしきりに首をかしげた。
女の子二人は、ならんで石垣にもたれている。大柄な有吉がひじを張るようにオーバーオールの前ポケットに両手を入れ、小柄な工藤のほうはかたをすくめるようにうでをせなかで組みながら、ほとんどなにも見えない空をじっと見上げている。
この二人がこんなに真剣になるなんて、ちょっと意外だった。
ミリがだれに言うともなくつぶやいた。
「星が見えなくたってへいきだよな。音を聞くのが目的なんだから」
みんなへの言いわけみたいな、自分に納得させるみたいなミリの言い方がおかしくて、ぼくは彼のせなかをつついた。
「そんな言いわけは通じないぞ。音が同時に聞こえるのを確かめるんだから、流星も見えなきゃこまるだろ」
「そうだったっけ。音だけ聞くんだったら、くもってても昼間でもいいんやけどなあ。あーあ。でも上野はいいよ。ぼくもそんな不思議な音じゃなくても、せめて爆発音くらい聞いてみたいなあ。パーンって」
ぼくは、ミリがこないだから紙でっぽうばかり作っているのを思い出した。あれはなにか意味のある事なのかなあ。……でも、意味のない事ばかりやるのがミリなんだっけ。
「でもな、見えなくても流星が流れたのを知る方法があるんだ。ラジオを使ってやる方法が」
ミリが言った。ラジオと聞いてダクテンはきょうみをしめし、頭の上にかかげていた星座早見盤を下ろすとこっちへやって来た。工藤たちも顔をこちらに向けた。
「FMラジオでな、ふだんは聞こえないような局が、流星が流れた時だけ聞こえるようになるんだってさ」
「どういう事?」
なんにでも好奇心おうせいな工藤が、石垣から身を起こしてたずねる。
「むずかしい事はわからんけど、流星が電波を反射するかどうかして、遠くの電波がとどくようになるんや。でもFMラジオじゃないとだめらしいけど。とにかくな、ふだん聞こえんような遠くの局にダイヤルを合わせておくと、ときどきちょっと音が聞こえたりするんや。それが流星の流れたしるしってわけ」
「でも、聞こえへん放送局にどうやってダイヤル合わすん?」
有吉がそぼくなぎもんを投げかけると、得意げなミリの表情がいっぺんにこわばった。その様子があんまりおかしかったので、ぼくらは大笑いした。
「ハハハハハ、どうもならんなあ、高橋計画パート2も」
「フハハ、そこまで考えてなかったのはあまかった」
「あまいんじゃないの、あんたはぬけてんの」
静まりかえったうす明かりの中に自分たちの笑い声だけがひびくのが、なんだかひどく不自然な感じだ。でもそれがかえって仲間の近さを感じさせ、気持ちのたかぶったぼくらの笑い声は、いつまでも夜の冷気をふるわせた。
「でもな、でもな、ちょっと聞いて。方法はあるよ」
ミリがなおも言ったけれど、やはりふざけた口調だったので、ぼくらも軽い気持ちで聞いた。
「流星が流れた時に合わせればいい。聞こえてる時に」
「流れとう瞬間に?」
「そ。すばやくな」
「そんなんできるわけないやん。願い事となえるよりむずかしいわ」
「願い事?」
自分でもびっくりするような大声で、ぼくは工藤に聞き返した。
「流れ星が流れるあいだに願い事をとなえると、その願いはかなうんよ。知らんかったん?」
「知ってるよ、それくらい」
でも謎を解明しようという時に、そんな事考えもしなかった。まったくこの二人は、なにを考えて空を見上げていたんだろう。
「はあ、まったく少女趣味にはついていけないよ」
「だってわたしら少女やもん。少女趣味でもええやないの。ねえ」
工藤は有吉と、おたがいに首をかたむけながら顔を見合わせた。
「あっそう。じゃあおれたちも少年趣味でいこうな」
ぼくはミリとダクテンに声をかけた。ぼくらに女の子の気持ちがわからないのと同じように、あの子たちにも電子工作とかのおもしろさなんてわからないんだろうな。そんなふうに思いながら。
ふと、あの二人は流星の音の謎を解くという事に、どのくらい熱意を持っているんだろうかと不安になった。まあこうして集まるんだから、きょうみくらいはあるんだろうけど。
「それ貸して」
ぼくはダクテンの持っていた星座早見盤を借りた。
「ちょっと流星のコースを確認しようと思って」
「そういやまだ聞いてなかったな。どう流れたん?」
ミリもかけ寄って来て、三人で星座早見盤を囲んだ。ぼくは指でコースをしめしながら、あの二人にも聞こえるように大声で説明した。
「真上よりちょっと東側から流れたんだ。だからこの辺りかな。それからずーっと西に向かって、たしかこの明るい星のすぐ横を通って……」
「ほんとに? こりゃすごいぞ、おい!」
ミリがふだんよりさらに一オクターブは高いさけび声をあげた。
「その流星、こと座を横切ってるよ!」
「なに? こと座を横切ったらなにがすごいわけ?」
「だっておもしろいやんか。流星がこと座を通りぬけて音を立てたなんて」
そういう意味か。ミリらしい考え方だと思うけど、これもなんだか少女趣味っぽいな。思った通りあの二人もきょうみをしめし、工藤が口をはさんだ。
「ことの弦ってわけ? 上野の見たんは」
「そう、上野はこと座の弦を見て、こと座の音を聞いたんやな」
「星の弦かあ……」
まさか本気で言ってるわけじゃないだろうなあ。月明かりにてらされて、工藤は夢見心地といった表情をうかべている。そのうちに両手を胸の前に組んでひざまずいたりして。……やめてくれよ。
「でもシューなんて音を立てたりするか? ことの弦がさあ」
「もう。上野、しらけるような事言わんといてよ」
「はいはい、わかりました。あれはことの弦です。星の弦です。でも……」
弦というより、と言いかけて、ぼくはあわてて口をつぐんだ。
こと座を横切って音を立てたあの流星は、弦というよりむしろバイオリンなんかの弓のような気がする。でもこんな思いつきを口にしたら、それこそ少女趣味だと言われそうだ。
こんな事を思うなんて、ぼくも月明かりにうかされてちょっと変になってるのかもしれないな。
11月4日 金曜日
あの夜以来、四人はぼくの事をゲン、なんてよぶようになった。
事情を知らないクラスメイトから、そうよばれるわけをたずねられたりしたけれど、そんな時はミリが、ゲンインフメイなんてちゃかして話をそらせてくれる。もともとそう関心があるはずもないから、だれもそれ以上理由をたずねはしなかった。
でもそれはべつとして、このゲンというニックネームは、じきにクラスの中でも定着していくような気がする。
秋の学校は行事が多い。こないだは秋の遠足があった。遠足はもちろん楽しみだけど、ほかにもっと大きな楽しみがあるせいか、あまり気持ちがもり上がらなかった。十一月に入って音楽会の練習もいよいよ大詰めだけど、それもやっぱりどこか気がぬけている。
ぼくが熱く、活発になるのは、放課後になってからだ。
けれども今日ぼくは、作文を時間内に書き上げられなかったせいで、放課後も教室に残されている。十五の集まりは、ざんねんながら中止になってしまった。
前の学校では作文なんてそんなに書かされなかったのに、ここではいやになるくらいたびたび書かされる。それでも好きな事を書かせてくれるならまだらくなんだけど、いつもテーマを決められるからもう大変だ。
今回のテーマはともだち。この前遠足に行ったからてっきりその事を書くのかと思っていたけど、あてがはずれた。先生の言うには、それはまた今度だそうだ。ぼくは何十回目かのためいきをついて、えんぴつをにぎったままほおずえをついた。
ちょっと上目使いに、ぼくは教室を見回した。工藤は教室のすみで学級文庫を読んでいる。有吉は自分の席で、新しいかべ新聞にイラストを描いている。テンとミリはろうかで立ち話をしているらしい。高さのちがう二人の影が、すりガラスごしにぼんやり見える。
四人とも、作文を書き上げたんならさっさと帰りゃいいんだ。帰る方向がちがうんだから、ぼくを待ってたってしょうがないのに。それとも、いつも四人そろって放課後残ってるものだから、それが習慣になってしまったのかな。
ぼくは原稿用紙に目をもどした。ともだちについて、ともだちの事、か……。どうでもいい事だけど、ミリやテンを高橋君とか山崎君とか書いてると、なんか調子くるうなあ。
ミリとテン、最初はどちらか一人の事だけを書くつもりだったけど、でもそれじゃ五枚も書く事なんてできやしない。それで、運動会でかつやくしたテンの事、そして予防注射で大さわぎしたミリの事を書いたけど、それでもまだ、三枚目の四行目の十二文字までしかうまっていない。
書く事がないのも、しかたがないさ。ぼくがこの学校に来てから、まだ二か月しかたっていないんだから。あともう二か月待ってくれたら、すばらしい作文を書き上げられる、かもしれないんだけどなあ。ぼくは何十一回目のためいきをついて、天井をあおいだ。
最近三人のあいだで話題になってる、電子工作の事でも書こうかな。それとも工藤や有吉の事を書くか。でもそうすると、十五夜の事まで書かなきゃならなくなるし。まあ秘密なのは流星だけで、星の観測の事くらいは書いたってかまわないだろうけど……。
今から会議があるとかで先生がいなくなってしまうと、入れかわりにミリとテンが教室に入って来た。この四人がそろったら、ぜったい静かに作文なんか書かせてくれないだろう、そんな予感がした。
思った通りだ。それまで静かに本を読んでいた工藤が、通りがかったミリの野球帽をひったくってにげた。
「あっ、こらユッコ、返せ!」
野球帽をかぶって窓ぎわににげる工藤を、ミリはさけびながら追いかける。静かだった教室がとたんにさわがしくなった。
テンも有吉も、それからほかのクラスメイトも、だまってなりゆきを見守っている。あおったりはしないものの、止めもしないんだから、やっぱりおもしろがっているんだろう。ぼくもこうさわがしくては作文に集中できないので、えんぴつを置いて二人の追いかけっこを見物した。
ミリは力ずくで帽子を取り返すのをあきらめたらしい。定規を持って工藤の席へ行くと、いすにかかっているカーディガンをつつき始めた。
「あー、そういう事していいと思ってるわけ?」
「じゃあ帽子返せ」
「やっ」
ミリは工藤のカーディガンを取ってそれを着ようとしたけれど、さすがにはずかしくなったみたいでとちゅうでやめた。そのあいだに工藤はミリの席に行って、今度はふでばこを取っていってしまった。
「おいこらユッコ、ひきょうやぞ。人質二つも取んな」
「ひきょうはどっちよ。人質に手あらなまねしといて」
二人のやりとりを聞いているとふき出しそうになる。まるでまんざいだ。
「どっちかかたほうだけでも返せ」
「いやっ」
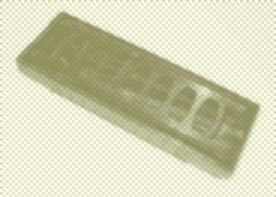 工藤はふでばこをゆかに置いて、それをふんづけるまねをした。ミリの声がいちだんと高くなる。
工藤はふでばこをゆかに置いて、それをふんづけるまねをした。ミリの声がいちだんと高くなる。
「わあ、やめえ。こわれるやろ!」
「ゾウがふんでもこわれないんとちがったん?」
「ユッコがふんだらこわれるんや。こらユッコ、待てっ」
ユッコはふでばこを持って教室を出て行ってしまった。
「おい、あいぼう。おうえんたのむ」
ミリはカーディガンを置くと定規だけ持って教室を飛び出し、あとからテンもしぶしぶといった感じで出て行った。教室がようやく静かになったので、ぼくは作文に意識をもどした。
やっぱりあとの二人の事も書こう。そう思いながらえんぴつをにぎった矢先に、ユッコが教室にかけこんで来た。そして真っすぐぼくのところに来た。
「ちょっとこれ持っとって」
そう言うと、ぼくが返事もしないうちにミリのふでばこをつくえの中におしこんだ。ミリたちがもどって来るころには、彼女はそしらぬ顔で自分の席にもどっていた。
「ほら、服は返しただろ。ユッコもその帽子返せ」
「それっ」
「投げるなって。それからふでばこは?」
「知らん」
「知らんはずないやろ。どこやった?」
「さがしてみ」
「まったく……」
ミリは自分のつくえやカバンの中をさぐり、それからロッカーをさがした。そこにもないとわかると、教卓や花びんの中までのぞきこんでまわった。
「ないなあ。ヨッシーはぼくのふでばこ知らん?」
「知らん。あたし新聞書いとったから」
よく言う。みんな見てたくせに。
ぼくだったら、ああうまくとぼけられるかな。ちょっと楽しみに思ったけれど、ミリはぼくも作文に熱中していたと思ったらしく、なにも聞いてこなかった。
「ほんとにどこにかくしたんや。あれは大事なふでばこなんやぞ。これからずっと大事に使って、いつまで使えるか新記録を作るんやから」
ミリはそうじ用具入れからほうきをみんな出してしまって、中に頭をつっこんでいる。ぼくはなんだかばからしくなってきて、つくえからふでばこを取り出した。
「ミリ、ほら」
「あーっ、うらぎった」
「ゲン、ユッコとグルになってたな」
両方からせめられる羽目になったけど、もうそんな事は気にしないで、ぼくは作文に集中した。ユッコの事、そしてヨッシーの事を書けば、あと二枚半くらいすぐうまるだろう。
「あ、ひどーい」
ユッコが後ろを指さしながら言うので、ぼくはふり向いた。ミリが後ろの黒板にらくがきをしている。
指名手配、という文の下にへたくそな似顔絵を二つ描き、その下に工藤由美子、上野康之とならべて書いた。それを見てユッコが立ち上がると、ミリは笑いながらろうかににげて行った。
次の章へ
 「あああれか。じゃあ、えーと、あれが北極星やな。ちょっと星座盤貸りるで」
「あああれか。じゃあ、えーと、あれが北極星やな。ちょっと星座盤貸りるで」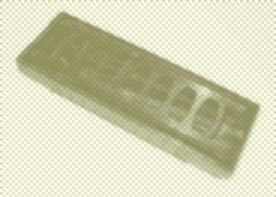 工藤はふでばこをゆかに置いて、それをふんづけるまねをした。ミリの声がいちだんと高くなる。
工藤はふでばこをゆかに置いて、それをふんづけるまねをした。ミリの声がいちだんと高くなる。